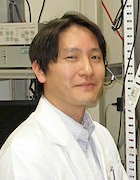|
グループ1 「iPS細胞技術による 視覚再生モデルの構築」 グループリーダー:川村 晃久 |
グループ2 「視覚系における回路形成・機能・認知のメカニズム解析」 グループリーダー:小池千恵子 |
グループ3 「視機能の理解と評価に向けた 細胞一回路一認知に渡る 視覚情報処理モデルの構築」 グループリーダー:北野 勝則 |
|---|---|---|
| 川村 晃久 | 小池千恵子 | 天野 晃 |
| 小池千恵子 | 三品 昌美 | 北野 勝則 |
| 高橋 政代 | 立花 政夫 | 篠田博之 |
| 大西 暁士 | 下ノ村和弘 | 徳田 功 |
| 十河 孝浩 | 北岡 明佳 | 坪 泰宏 |
| 植山 萌恵 | Steve H. DeVries | 竹田有加里 |
| 塚本 輔 | Robert Lading | 姫野有紀子 |
| Nguyen Quang Anh | Muangkram Tuttamol | |
| 二木 大樹 |
グループ1 iPS細胞技術による視覚再生モデルの構築
川村 晃久 立命館大学 生命科学部 生命医科学科 准教授
・グループリーダー
・iPS細胞樹立チーム チームリーダー
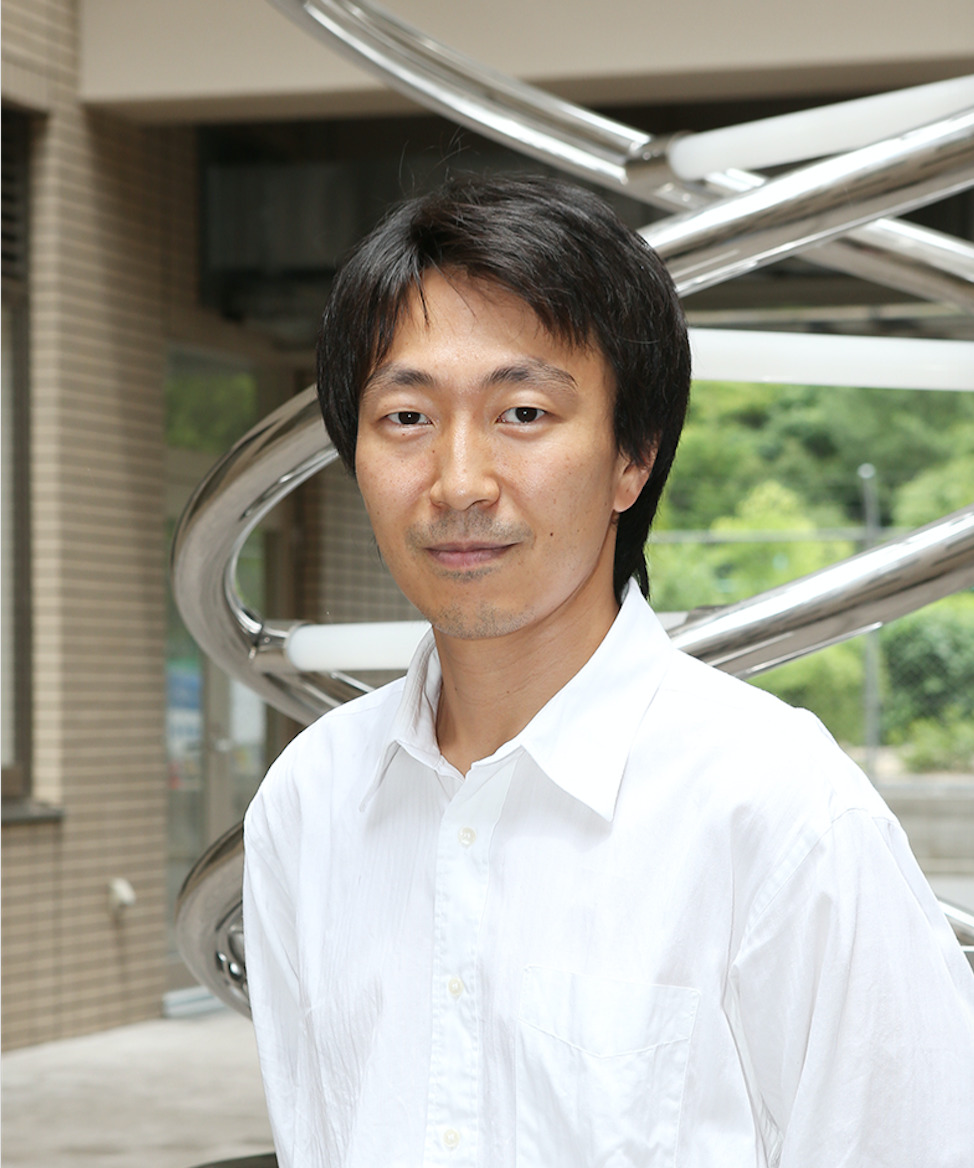
視覚・神経系の難病や心不全などの臓器不全に対して安全かつ効率的な
再生医療を実現化するために、遺伝子発現によるリプログラミング(初期化や形質転換など)
の技術を駆使した幹細胞生物学の研究をしています。
小池 千恵子 薬学部 創薬科学科 准教授
・三次元網膜作成チーム チームリーダー

網膜回路が視覚応答にどのように関わっているか、網膜視覚伝達系の中間ニューロンにあたる双極細胞に注目して解析を進めています。視覚応答系の開発・解析だけでなく、組織化学解析や電気生理、分子生物学や生化学の手法を用いて網膜視覚系の解析を神経発生の面からも多角的に行っています。
高橋 政代 理化学研究所

最近まで障害されると再生しないと思われていた成体ほ乳類網膜が、少なくとも傷害時に網膜神経細胞を生み出す力をもっているらしいことがわかってきた。このことは、成体網膜も神経回路網を再構築する能力を秘めているのかもしれないと期待させる。この力を使って、網膜の中から、あるいは外から細胞を移植することによって、疾患で失われた網膜機能を再生させたい。また、iPS細胞を用いた網膜細胞移植の実用化を目指している。しっかりした基礎と臨床の研究を積み重ね、両者をふまえた網膜再生研究を行いたい。
大西 暁士 理化学研究所
植山 萌恵 立命館大学生命科学部生命医科学科 D1
塚本 輔 立命館大学生命科学部生命医科学科 D1
グループ2 視覚系における回路形成・機能・認知のメカニズム解析
小池 千恵子 薬学部 創薬科学科 准教授
・グループリーダー

網膜回路が視覚応答にどのように関わっているか、網膜視覚伝達系の中間ニューロンにあたる双極細胞に注目して解析を進めています。視覚応答系の開発・解析だけでなく、組織化学解析や電気生理、分子生物学や生化学の手法を用いて網膜視覚系の解析を神経発生の面からも多角的に行っています。
立花 政夫 総合科学技術研究機構 教授
・機能解析チーム チームリーダー
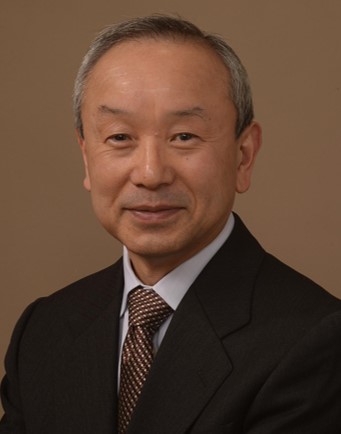
眼球の光学系によって投影された外界像(網膜像)は体・頭・眼球の動きによって網膜上で常に揺動している。網膜はこのような動的画像をどのように処理して符号化し、視覚中枢に送っているのかを神経科学的手法を用いて研究している。
下ノ村 和弘 理工学部 ロボティクス学科 准教授
・行動解析チーム チームリーダー

ビジョンを中心としたセンシング技術・ロボット知能化技術の研究を行っています。センサデバイスやカメラ、画像処理アルゴリズムの開発、ロボット制御や生体情報計測への応用、また、生体視覚系のモデリングなどのテーマに取り組んでいます。
北岡 明佳 総合心理学部 総合心理学科 教授

錯視研究の第一人者であり、錯視の心理学的な研究とともに、錯視を利用したデザインにも取り組んでいます。多くの錯視画像を考案し、書籍の出版や展覧会を開き、自身のWebサイトでも「北岡明佳の錯視のページ」を公開しています。
Steve H. DeVries Northwestern University

Parallel processing of the visual input under daylight conditions begins at the mammalian cone photoreceptor synaptic terminal. At this terminal, a single cone employs 20 transmitter release sites to communicate its signal to 12-13 different types of post-synaptic retinal bipolar cells. We use electrophysiological, super-resolution microscopic, and optogenetic techniques to determine how the 3D structure of the cone synapse helps to create different electrical signals in the different bipolar cell types. These different signals, in turn, form the basis of the excitatory responses of the ~30 types of retinal ganglion cells, which send their axons to the rest of the brain in the optic nerve.
グループ3 視機能の理解と評価に向けた
細胞一回路一認知に渡る視覚情報処理モデルの構築
北野 勝則 情報理工学部 知能情報学科 教授
・グループリーダー
・機能的回路モデルによる視覚情報処理機構の解明 チームリーダー
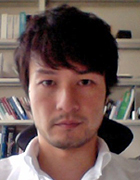
脳機能の柔軟性は、脳神経系の構成要素であるニューロンやシナプスが示す多様な動的特性がもたらすと考えられます。神経系の数理モデルを構築・解析することで、それらの動的特性や脳機能の仕組みそのものの理解を目指しています。
天野 晃 生命科学部 生命情報学科 教授

生体を構成する個々の要素に関する情報は急速に増大していますが、これらの個々の要素がどのように関係して組織、臓器や個体の機能を実現しているかは未知の部分が多く、今後ライフサイエンス分野の研究の大きな柱になると考えられています。本研究室では、ライフサイエンス分野の研究成果である個々の要素機能を組み合わせてより規模の大きな機能要素のシミュレーションモデルを構築することで、組織や臓器の機能がどのように実現されているかを研究しています。
篠田 博之 情報理工学部 知能情報学科 教授

視知覚・認知メカニズムの解明を目指して、心理物理学的手法を用いて人間視覚系の特徴を研究しています。その応用として、人の感覚量に適合した新たな物理指標や尺度を提案し、産業界における人中心のものつくりや設計に役立てています。
実験において計測不可能なパラメータを、多電極計測によってい記録されたスパイクデータから逆推定する方法について紹介する。特に、数理モデルと実験システムの間に生じる複雑性の乖離やデータの非定常性などの問題について議論する。
大脳皮質における情報処理原理を「局所回路」という構造に注目して解明し、新しいコンピュータの仕組みを築きあげることを目指しています。「局所回路」をキーワードに様々なアプローチをとることで、物理、工学、神経科学それぞれに対し新しい視点と世界を見つけられるのではと期待しています。
理論研究によって生体機能を細胞レベルで理解することを目指しています。これまでの生理学実験経験を活かしてさまざまな細胞モデルを構築し、バイオシミュレーションやその数値解析によって、細胞機能制御機構を定量的・包括的に解明することに取り組んでいます。